| コンペンディウム・マレフィカルム 第2巻第2章 魔女が人の屍骸を用いて人を殺傷すること 論拠 昨今、魔女が屍骸を掘り返して人を殺傷することに用いることが慣習となっている。とりわけ死罪や絞首刑に処せられた人間の屍骸が用いられる。魔女はかくもおぞましき材料から魔力を更新するのみならず、処刑に際して用いられた道具すなわちロープや鎖や杭や鉄製品も重用する。事実、この種の物品に固有の魔力が宿るという信仰が広く流布している。 他の魔女は屍骸を調理して灰状にし、ある種の物質と混ぜて固形の練り物とする。ジョヴァンニ・デラ・ポルタもかれの時代にその種のことが行われていたと触れているし、プリニウス(博物誌27巻7章)も語っている。われわれの時代では、ドイツ領ロレーヌにてこの種の事例を多数裁いたと報告している。 |
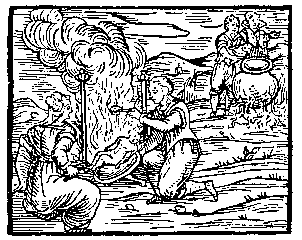 |
|
実例 1586年10月15日ドウジーにおけるアンナ・ルファの告白によれば、彼女はロラなる名前の魔女が埋葬されたばかりの遺体を掘り出す手伝いをしたという。両名は屍骸を焼いた灰から薬を作り、他人を殺傷する際にこれを用いている。 1587年8月ヴォルパシュにおける魔女ブリシアの証言によれば、父親である鍛冶屋のウォルフによって二日前に埋葬された息子の死体を魔女が掘り返している。先に引用した件と少し違う部分は、死体を灰にせず、溶かして固形にしている点である。そのほうが膏薬に加工しやすいからである。しかし骨は灰にして果樹園の木々に散布し、実がなることを阻害したという。 1588年12月グエルミンゲンにおいてアントニー・ウェルチは魔女仲間のニチェル・グロスとベスチェスの妻が語った内容を報告している。魔女たちはグエルミンゲンの共同墓地に埋葬された屍骸を二体掘り出し、焼いて灰にしてよこしまな魔女の術に用いたという。しかし焼く前にまず右腕を肩とわき腹の部分から切り落としている。これは先に触れた悪魔の松明を作る際に必要なのである。夜間にだれかに毒を盛ろうと思うとき、魔女たちは死体の腕の指先に火をともす。するとそれは魔女たちが仕事を終えるまで青い硫黄臭を放つ炎をともすのである。そして炎を消したときも、指先はまったく焼けず、減りもしていない。なんど用いてもこの通りになるという。 |
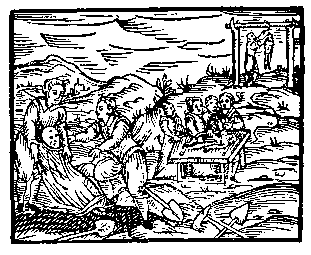 |
|
ウェルフェルディンゲンのヨハン・ミュラーには一歳の愛児がいた。ピッテルリンゲンのアガティナとホーヘンエックのマイエッタがこの赤子を揺り籠から盗み、ラ・グリスと呼ばれる丘にまえもって用意しておいた焚き火で焼き殺している。両名は残った灰を慎重に集め、これに穀物と草の穂から採取した露を混ぜて、ぽろぽろと崩れやすい状態にしている。魔女たちはこの粉末を葡萄や作物や樹木に散布し、花を枯らせ、実がなることを阻止したという。 |
|
|
| 解説 : ふたたびフランシスコ・マリア・グァッゾの『コンペンディウム・マレフィカルム』(1608)からの抜粋である。死体盗掘から人脂処理という嫌な話題が中心となっているが、この記述で注目すべきは例の「栄光の手」のロング・ヴァージョン、および青い炎と硫黄臭という具体的描写である。他の作家にも登場するこの不気味な催眠誘発剤は、なんらかの裏付けがある存在なのか、まったくのファンタジーの産物か。ファンタジーにしてもファンタジーなりの裏付けがあるのか否か。ものがものだけに再現実験もままならず、結論が出ぬまま現代に至ったものと思われる。 |