| 『ロンドン・ミステリー・マガジン』1950年第1巻5号。 いまだ紙の統制が続く戦後のロンドンにて刊行されたミステリー専門誌である。刊行元住所がベーカー街221−Bという凝りようで、ヴァラエティーに富むイラストが目をひく。内容的には怪奇や幻想系も多数採用されており、毎号アルジャーノン・ブラックウッド等が紙面を飾っていた。 この5号には当時の著名ジャーナリストであるスウェイファーが「ある芸術家の謎」という一文を寄せている。それを訳出しておくのが本稿の目的である。 |
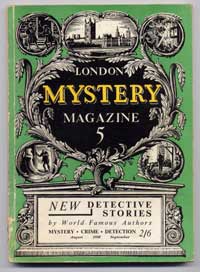 |
|
|
|
| 『ロンドン・ミステリー・マガジン』1950年第1巻5号。 いまだ紙の統制が続く戦後のロンドンにて刊行されたミステリー専門誌である。刊行元住所がベーカー街221−Bという凝りようで、ヴァラエティーに富むイラストが目をひく。内容的には怪奇や幻想系も多数採用されており、毎号アルジャーノン・ブラックウッド等が紙面を飾っていた。 この5号には当時の著名ジャーナリストであるスウェイファーが「ある芸術家の謎」という一文を寄せている。それを訳出しておくのが本稿の目的である。 |
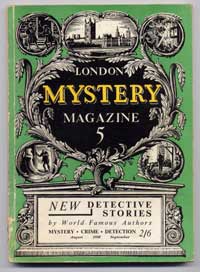 |
|
|
|
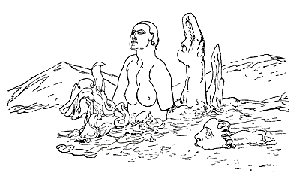 |
||
| ある芸術家の謎 ヘイネン・スウェイファー オースティン・オスマン・スペアという芸術家の謎はいかなるものなのか、私は長らく不思議に思ってきた。これほどの天才がなぜに脚光や芸術サロンに目もくれず、ろくに家具もない地下室で暮らしているのか? なぜに芸術あふれるチェルシーでもブルームズベリーでもなく、ブリクストン・ロードというぱっとしない場末で野良猫に囲まれているのか? |
Swaffer, Hannen 1879-1962, 当時の有力ジャーナリスト。美術批評や劇評を得意とし、心霊術にも造詣が深い。 | |
弱冠17歳にしてサージェントから「天才」という言葉を贈られた男が、なぜに実入りの多いキャリアに背を向けて、自らの出身地でもあるロンドン南部の労働者たちに混じって暮らし、後世きっと傑作と称えられるであろう絵画をわずか5ポンドで売っているのか? 少しおとなしい作品を出せば王立アカデミーに大歓迎されるだろうに、なぜにこの画家はウォルワース・ロードの居酒屋で個展を開くのか? そしてかれが語る「自動描画」と「妖術」とはなんなのか? 「死んだ画家たちの霊」がかれを通して絵を描くとは、どういう意味なのか? おそらくスペア本人以外で、以上の質問に答えられる人間は私しかいないだろう。私はスペアの作品の収集家であり、かれと長らく語り合ってきた。おかげで本人の口から鉛筆と油絵の使用法に関する理論や、夢のこと、野心がまったくないことなどを聞き出すことができたのだ。 私がオースティン・スペアの名前を初めて目にしたのは1904年、通勤列車でデンマーク・ヒルズの自宅に帰る途中のことだった。ウォルワース・ロードにあるサウス・ウォーク図書館、その壁面に貼られたポスターにかれの名前があったのだ。わたしは途中下車し、図書館に入って16歳の少年が描いた作品を見学した。その少年はロンドンの警官の息子であり、すでにその前年にバーリントン・ハウスに作品が展示されていた。同美術館の長い歴史のなかでも最年少の展示者であった。「スペアの業績はすでに名声を得て当然の域に達している」とG・F・ワッツが評していた。 このときの個展の内容は正直いって覚えていない。ただ描線の尋常ならざる律動と目を奪われるほどの独創性ゆえにそのときの体験と画家の名前だけは決して忘れなかったのである。年月がすぎ、おそらく1926年頃だったと思うが、スペアから招待状が届いたのだ。当時われわれはまったく面識がなかったわけだが、ともあれエレファント・アンド・カッスル近くにある労働者住宅街の家まで絵を見にきてほしいという。かれが描いていたのは地元の人物や娼婦や行商人たちであった。裕福なパトロンたちを描くよりもこちらのほうが性に合うという。ハワード・ド・ウォルデン卿やサー・フランク・ブランギンといったお歴々がわざわざ出向いてかれの作品を買い上げているにもかかわらず、である。そしてかれは「サイドレアリズム」と自ら称する新たなスタイルで実験を繰り返していたのである。 このスタイルのために、かれが描くポートレイトは奇怪な遠近感を持つ。顔は水平方向にも垂直方向にも力感が薄れ、ひずみや傾斜すら帯びるようになる。油絵になればステレオスコープ的意味合いを持ち、誇張はするが本来の類似性を破壊はしないのである。 かれは慎ましい労働者たちを友とし、かれらの陋屋の真っ只中で暮らしていた。その種の貸し部屋のひとつにおいて、かれは初めてオカルトの話をしてくれた。いわく寝ているあいだに絵を描いたとか(そのうち最良の2枚は私が所有している)、あるいは長年の実験の結果、自室のなかに雨を降らせたとか。かれは貧乏な暮らし向きであったが、生まれ育ったサウスウォークの労働者たちに囲まれて至福を感じていた。これぞ自分の属する場所という思いが強かったらしい。 それから1939年の戦争が到来した。他のコクニーたちと同様、かれも空襲をものともせず、何ヶ月ものあいだ不発弾の上で寝るような生活をしていた。しかしついに1941年5月、空襲と火災のためにかれのスタジオが焼け落ち、自宅も半焼した。かれは作品も画材も健康も失った。かれの右手は麻痺し、また社会保障面の不備と遅れから、冬の5ヶ月間をわずか9シリングで凌ぐという惨状に直面したのである! 誇り高いかれは他者の援助を請うことをせず、私にすら窮状を悟らせはしなかった。再会したとき、かれは病気になっており、ぼろをまとっていた。 以来かれは徐々に回復し、指も動くようになっている。相変わらず労働者階級の界隈で個展を開き、労働者階級の値段で売却し、富裕層が申し出る庇護を鼻でせせら笑い、貧者の家庭に芸術愛好を持ち込むことをよしとしている。 |
||
 |
||
| 現在、私の部屋の一壁面にかれの絵が七枚掛かっている。それぞれスタイルと個性がまったく違うため同一人の手になると思われる絵は一枚もない。さらにトラファルガー広場を見下ろす居間のテーブル上に3冊のスケッチブックがある。いわゆるかれの「自動描画」がやまほど描いてあり、どれもみごとな線である。またあまりに大胆なコンセプトゆえに唯一無比の画集といってよい。 さらに私は別に二枚を所有している。スペアが暗闇のなかで描いたものであり、死んだ画家の霊による作品だそうである。出自はともあれ、二枚とも心霊をテーマとしている。残念なことに、きわめて繊細な鉛筆画であるため、壁に掛けるわけにはいかない。細部を見るにはよくよく接近しないと無理なのだ。それでも比類なき腕前の作品であることは疑問の余地がない。両者とも、人知を超える広大な存在域における霊魂の進化を描いているように思われる。それぞれ題名は「意識の溶解」、「堕ちたる者たちの上昇」となっており、そのよこに「自動描画」という言葉が書いてあった。 「一部の作品の背に自動描画と書いてありますが、これはどういう意味ですか?」と私はかれに質問したことがある。 「それは単に、絵を描いているときに自意識がなんらかのものを認識していなかったという意味だ」とかれは説明した。「描いているときよりも、描き終わったときにわかることが多い。つまり、紙に描きだしてみてはじめて意識することが多い。そうでない場合は、自動的にはならない。自分の潜在意識はそれを意識しているだろうが、通常意識のほうはわからないわけだ。 「一番わかりやすい例を出すなら、そう、作業をしているときは自分がなにをしているかわかってない場合が多い。自動的に作業しているんだ。それから通常意識状態に復帰する。部屋の中は真っ暗になっている。ほとんどなにも見えない闇のなかで仕事をやり終えていたわけだ。 「仕事をしているあいだに明かりは落ちたんだろう、多分。それでも闇のなかで作業をしていた。仕事の速さは驚異的だった。比喩を用いるなら、ほとんど“光速”で作業をしていたよ。 「あなたが買った自動描画の本の一冊には、差異をはっきりさせるために二枚ほど“意識的”作品を入れてある。丸一冊仕上げるのに4時間しかかからなかったが、最後の二枚は違う。それは意識的精神を投影した作品だからだ。他の作品はすべて純粋に自動描画として描きはじめている。手の好きにさせていたといってもいい。手が動きおわり、出来上がった結果が樹を思わせるものであれば、線を少し描きたしてより樹木らしくするだけだ。動物や人物を思わせるものだったら、最小限の円や曲線を入れる。 「自動描画に入っているとき、わたしはだれか画家の霊、おそらく死んだ画家の霊に取り憑かれるというか、乗り移られている。正確にはわからない。証拠といわれてもこまるが、作品がデューラーやブレイクに似ている、あるいはまったく知らないだれかに似ているとか、そういうあたりしかないだろう。 「作業の初期段階で部分的に自動的になっている画家や作家や音楽家は多いと思う。潜在意識とはちょっと異なる、擬似意識状態で機能しているんだ。創造的人間はみなこの能力を持って生まれてくる。その上に勉強や練習を重ね合わせていくんだ。他の能力や才能と同様、これも育てることができる。 「芸術や著述における“自動”を定義するならば、意識的精神がなんらかの外的存在に占有されている状態、あるいは手の活動を精神がまったく意識していない状態というところか」。 |
||
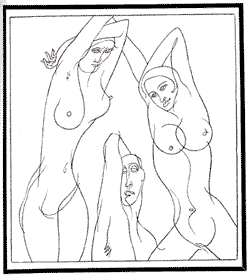 |
← この記事を飾る自動描画と対比するため、左にスペアによる意識的な運動研究を載せておく。かれが線の達人であることが窺えるであろう。かれの天才を真に鑑賞するには、できれば絵画制作の現場を生で見学するしかないといっておく。(スウェイファー) |
|
十代半ばにしてオースティン・スペアは抽象を主題とする絵を、たとえば混沌の絵画などを描いていた。「おそらく病的なものだったと思う」とかれは言う。「一部は自分の作品だったと思う。だれか他人の作品だったものもあると思う。それから『アース・インフェルノ』という本を出した。解説のかわりに自分流のダンテを描いたんだ。マスコミは驚倒したよ。あらゆる新聞から“天才”と称賛されたな。500部印刷したが完売した。一冊あたりの経費は5シリングだった。それに自分で着色して一冊1ギニーで売ったものさ。 「それから5年間くらいははモノクロでやっていた。とりあえず食えたよ。1914年の戦争のちょっと前に『快楽の書』というのを出した。これもマスコミに大いにうけた。神秘主義に関する本でね。デイリー・テレグラフ紙のサー・クロード・フィリップにはずいぶんとほめてもらった。それで他の新聞も右にならえになった。おかげで神秘主義の画家という立場が一応確立された。結構うまくやっていたと思う。それから『フォルム』という文芸美術誌を編集した。 「戦争が始まったとき、自分は陸軍に入った。除隊になったとき、世界の様相は一変していた。まったく違う場所になっていた。以前のやり方では世の中についていくのがとても難しいことがわかった。それでいよいよ抽象の世界に入っていった―以来ずっと、つかずはなれず抽象の世界にいる 「オカルトの知識をちらちら見え隠れしている点に関していえば、自分は子供の頃からそういったものを持っていた。1914年の直前に発達しはじめ、以来ずっと発達している」 「方法はわからないが、自分が異界に影響されているという説明を受け入れてらっしゃる。そうおっしゃいましたね?」私はスペアに言った。 「そのとおり」とかれは答えた。「だが理解できるとも思えない。作品間の差異を見れば、影響があったかどうかを判断することはできるだろう。ただのポートレイトの場合もある。純粋なリアリズムのときもあるし、まったくのシュールレアリズムのときもある。象徴主義のときもあれば、混ざり合うときもある」 「あなたは黒魔術を信じますか?」 「どう呼ぼうかまわない。妖術と言ってもいいだろう。そちらのほうがあたりさわりが少ないと思う。個人的には魔術に黒も白もないと思っている。世界中の色彩が黒と白しかないというなら話は別だろうが」 |
||
| ここで私はスペアの占いの能力に触れなければならない。かれは一組のカードを使って「未来を読む」のである。そのカードもかれ自身がデザインし、色を塗った特製の品なのである。「占いはもうやらないことにしているんだ」とかれは言う。「客の未来になにが見えたか、あえて口にする気が起きない。真実を隠したくはないが、なにもかも告げるわけにはいかない場合も多い。こちらはみんなわかっているんだが。まったくの悲劇を予知しても、そうなるまえに人生が終わる客も多かったわけだし 「カードを読む能力は子供の頃、ある老婦人から貰った。101歳まで生きた人だった。うちの両親の友人で、自分もほんの子供の頃よく占ってもらった。その予言が細部にいたるまで正確だったのでみんな感心していた。医者の奥さんだったけど、ジプシーの血が流れていた人だった。あれほどすばらしい女性に会ったことはない。だれにでも親切でやさしくてね。子供のような人だったよ。そりゃあ荒れた場所に住んでいたが、たいがいの荒くれどもも彼女のことは尊敬していた。 「ようするに彼女は一個の人物として自分の心に刻まれたわけだ。亡くなったときも、最初に会った頃とほとんど変わりがなかった。40年ほどまえ、彼女のもとに有名人を連れていったことがある。かれらについてはなにも知らないはずなのに、すべてはお見通しだったよ。彼女は生まれつきの催眠術師でね、“あの暗い隅を見てください”と言ったものさ。言われたとおりにすると未来に関することを映像化して見せてくれたよ。 |
See A.O.Spare, TwoTracts on Cartomancy, Fulgur, London,1997. | |
| 「一度クリフォード・バックスを彼女の家に連れていった。もちろん彼女は名前も知らなかったと思う。それでも誰にも教えてもらえないようなことを当てていた。二度結婚するだろう、寿命はいつまで、と言っていた。クリフォードもびっくりしていた。 「オーブレー・ビアズリーの姉のメイベルを連れていったときは、あとで老婦人からこっそり言われた。自分の口からはとても言えないけれど、あの女性の命はあと2年しかないから、と。それから2年後、メイベルは療養院で亡くなった。癌だったと思う。メイベルはその場ではなにも言われず、ただ励まされ、いい気分で帰っていったよ。いずれ襲ってくる病魔に関しては、ただ“健康に気をつけて”としか言っていなかった。ただ、老婦人はわたしにはとても正直に語ってくれていた。わたしの人生の主要な節目に関しては全部教えてもらった。わたしは一回占いをすると、たっぷり4時間は睡眠をとりたくなる。でも老婦人は疲れも見せずに何百回もできたんだ」 |
Clifford Bax 1886-1962) 当時の有力な作家、劇作家、何でも屋。クロウリーとも知己であり、スペアとは美術文芸誌 The Golden Hind(1922-24)を共同編集している仲。 | |
|
オースティン・スペアはたいがいの幽霊話は相手にしていなかった。いわく田舎の暗い道では「樹木のシルエットがお化けに見える」とのこと。それでいてこうも言っている。「そういった錯覚と本物の差異は、虎の絵を見ることと実物の虎に出会うことの差に等しい」。 |
Robert Hugh Benson (1871-1914) 当時の著名な文人にしてカトリックの高位聖職者。英国国教会の名門に生まれるもカトリックに改宗。聖務の傍ら怪奇小説を出して評判をとる。兄弟にやはり怪奇で有名なE.F.ベンソンがいる。 | |
 |